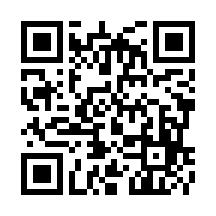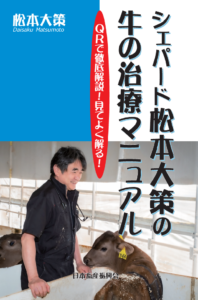2025年10月31日 *********************************************************** 手順を追って説明します。 1. ウェブアプリを開く
2. ウェブアプリをスマホのホーム画面に追加する 【Androidの場合】 【iPhone】 ホーム画面に追加すると、以下のような感じになります。すぐに使うことが出来るため非常に便利ですが、追加しなくても使用はできます。 3. 子牛の胸囲を測定する 測定に使うメジャーは何でも良いです。私は裁縫用の100円くらいのメジャーを使っています。 胸囲の測定方法は全国和牛登録協会の方法を参考に行います。具体的には子牛を正姿勢にし、肩甲骨後縁の指二本分後ろの位置でメジャーを巻きます。メジャーは最初にやや強く締め、その後緩め、その中間の目盛りを確認します。 測定時の子牛の姿勢は大事です。首を曲げたり、頭を下げたりすると数値がズレてしまうためです。 4. ウェブアプリに情報を入力する この結果を記録したい場合は、保存を選択します。保存すると、画面下の記録一覧に記録されます。 さらに2頭以上を同様に測定、入力、保存を行うとグラフ(散布図)が表示されるようになっています。測定した牛の平均胸囲充足率、近似直線の傾きも表示されます。 5. 牛群の発育の傾向を確認する では例として、下の結果をご覧ください。これはとある農場で21頭の子牛を測定した結果になります。 結果は平均胸囲充足率が96.2%、傾き(近似曲線の傾き)が-0.07となっています。この結果から、測定した牛群は日齢を追うごとに発育が若干遅れ気味になっていることがわかります。飼養管理見直しなどの対策することで、平均胸囲充足率も高くなり、さらに病気に強い牛群に出来る可能性もあるということです。 また個別の胸囲充足率を見ていくと、牛群の中で明らかに発育が遅れた牛がいることがわかります(赤丸)。 こういった牛は過去の治療歴などを調べると、「低体重で生まれた」「下痢が長引いた」などの何かしら異常があることがあります。そういった場合は、個別に対策を考える必要があります。また将来的に病気しやすいこともありますので、哺乳期間の延長や脂肪酸の添加などの対応を検討しつつ、要注意牛として頭にいれておく必要があります。 このように日齢をバラけさせて複数頭測定することで、牛群の傾向を把握することもできます。可能であれば哺乳期から離乳後まで測定すると、離乳の影響なども調べることが出来るためオススメです。 長文になってしまいましたが、以上が現時点でのざっくりとした使い方になります。他にも結果のCSV出力などの機能もありますが、今回は割愛します。 ウェブアプリの機能に関しては、今後もアップデートする予定です。何かご意見やご質問、ご相談などありましたら、ぜひホームページの「ご質問・ご相談」コーナーなどから教えていただきたいです。 前回のコラムでも触れましたが、DGや胸囲充足率のように発育を数値化するということは非常に重要だと感じています。ぜひ今回のコラムやウェブアプリがご参考になれば!と思います。 皮下注射や静脈注射、気管内注射などの仕方も解説しています。わかりやすいようにQRコードを付けてあるので、スマホをかざせば動画も見られますよ。 10月末発売。 |
![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)





 尿でわかる!マイコトキシン検査のご案内
尿でわかる!マイコトキシン検査のご案内