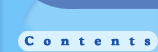|
クレアチニン② |
コラム一覧に戻る
2023年2月17日
今週の14,15日は獣医師国家試験の実施日でした。受験生の皆様お疲れさまでした。引っ越しの準備など、これから忙しいとは思いますが、少しばかりゆっくりしてください。本当にお疲れさまでした。
前回のコラムではクレアチニンがどのように出来上がるのかをお話ししました。肝臓でクレアチニンのもととなるクレアチンが作られ、筋肉で代謝されクレアチニンとなり、尿中に排泄されることをお話ししました。またクレアチニン値が低い状態についてもお話ししました。
今回はクレアチニン値が高い状態についてお話ししたいと思います。
クレアチニンは血液中の老廃物ですので最終的に尿として排出されます。尿は腎臓で血液中の老廃物や塩分を濾過して作られます。ここで腎臓に異常がある場合、クレアチニンが濾過されずそのまま血液中に残ります。こうして腎機能が低下すると血液中のクレアチニンが高値になるのです。
血液検査でのクレアチニン値は血液中の濃度として示されます。脱水状態の時は血液の液体成分が少なくなるのでクレアチニン値が高くなります。また脱水時は尿の量も少なくなるため、排出されるクレアチニンが減ります。結果的に通常よりも多く血液にクレアチニンが残るため、検査値が上がるのです。
ちなみにクレアチニンは先に記した通り筋肉内で産生されるため、筋肉量が多い去勢の肥育牛や種雄牛の方が高くなることがあります。
まとめますと、クレアチニン値が高くでた場合は腎臓病や脱水の可能性を考えます。実際にはクレアチニン単体で考えるのではなく、BUNやヘマトクリット値など他の血液検査項目の結果や、便性状や聴診、視診といった診察の結果から牛の状態を考えるのです。
 今週の動画 今週の動画
ナックル子牛 副木固定にチャレンジ
前の記事 クレアチニン① | 次の記事 お産トラブル時の薬~ホーリン編~ |
![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherdtest-1.4.1/images/header01.gif)