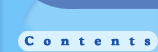2017年9月29日 では、膵炎とは?というと、『膵臓の外分泌』の部分の障害です。前回、膵臓の外分泌は『トリプシン』というタンパク分解酵素だと言いましたが、ちょっと説明を省いた部分があります。少し詳しく言うと、膵臓をはじめ、動物の身体はすべてタンパク質で出来ているので、膵臓から『トリプシン』をそのまま分泌すると、膵臓自身を消化して溶かしてしまいます。膵臓から十二指腸に膵液(外分泌の『トリプシン』を含んだ消化液)を運ぶ膵管も溶かしてしまいます。そこで、膵臓から分泌されるのは、『トリプシン』になる直前の『トリプシノーゲン』という前駆物質で、タンパク質の消化能力を持たない物質なのです。『トリプシノーゲン』は、十二指腸で肝臓から分泌される胆汁と反応して、始めて『トリプシン』に変化してタンパク質の消化能力を持ちます(それじゃ、どうして十二指腸は溶けないのか?というと、タンパク質ではない『粘液』で保護されているからです)。 ちょっと回りくどくなりましたが、もしも膵管を胆汁が逆流したらどうなるでしょう? 膵臓や膵管の中でトリプシノーゲンが活性化し『トリプシン』になってしまいます。すると膵臓や膵管のタンパク質を溶かしてしまいます。これが膵炎で、(写真1)にあるように膵臓が腫れてしかも硬く変化しています。 もともと膵液を分泌する膵管と胆汁を分泌する胆管は、別の位置(同じファーター乳頭という出っ張りにはあるのですが)に開口しているはずなのですが、牛さんによっては、途中で膵管と胆管が一本に合わさって十二指腸に開口していたり、同じ部分に開口していたりする奇形が存在します(人間も同じで、実は僕もそうなのですが)。そうなると胆汁が逆流しやすく、膵炎を起こしやすいのです。 実は今回のお話しのメインですが、血液検査の異常値で稀にGGT(γ-GTPともいっていました)のみが上昇している例の相談をお受けすることがあります。GGTの上昇というと、誰もが肝臓の障害を疑うと思います。しかし、肝臓の障害の時は、AST(以前はGOTと呼んでいました)の上昇も伴いますが、GGTが単独で上昇している牛さんもいるのです。そしてそういう牛さんを解剖して調べても肝臓は正常です(写真2)。 こういう牛さんは、まず膵炎を疑うべきだと思います。これは何例も解剖に立ち会って確信しています。では、なぜGGTが単独で上昇しているのか?それは、GGTというのは胆管に含まれる酵素で、胆管が傷害されると細胞が壊れて血液中に出てくるのです。胆管は肝臓の中に網の目のように通っているので、肝臓の障害の時はASTとともにGGTが上昇します。 これはあくまで推測なのですが、膵炎の時は、胆汁が膵管に逆流したように、活性化してタンパク質を溶かしてしまう『トリプシン』を含んだ膵液も逆に胆管を逆流して胆管を傷害するのではないか?と僕は考えています。 前の記事 牛さんの膵炎のお話し その1 | 次の記事 どっちだ? |
![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherdtest-1.4.1/images/header01.gif)