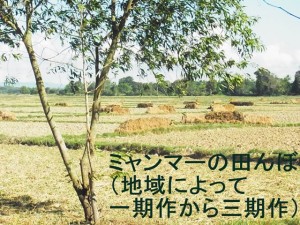|
イナワラについて思っていること その2 |
コラム一覧に戻る
2012年12月17日
松本です。
前回稲ワラのことを書きました。その続きです。
まず、掲示板で話題になっていた稲ワラの輸入に関する条項は、この稿の最後にまとめます。
僕が一番言いたいのは、祖国の農業の一環として畜産を考えるのであれば、国産稲ワラの自給率向上を本気で取り組まなければならない!ということです。
この点に関しては農水省もかなり真剣に取り組んでいるのですが、農水の方からのお話しでは「発生量(約850万㌧、飼料向け約86万㌧)は畜産が利用する量(約100万㌧)(輸入約20万㌧)からすれば充分に間に合うのですが、稲の収穫機械や西日本の刈り取り後の天候不順から乾燥ができないため、自給率は上がっていません。」ということでした。力不足ですみませんという個人的なコメントもいただいていますが、農水の取り組みがなければ、さらに利用率の低下があったことは、想像に難くありません。
僕は、生産者側からの知恵や努力も提示して、一緒に解決できないか?と思うのです。そこで前回は、あのような稚拙ですが、他の省庁の予算なども使えないかと提案したわけです。
ただ、同時に僕はリアリストでもあるので、フェイルセーフの観点からも、中国だけでなく、他国からの入手も進行しておくべきだと考えているのです。
ですからこの点に関しても、農水の方から方法論を伺ったところ、
「まずは、輸出禁止区域の輸出を望む国から申請が出て、両国の病害虫の発生状況や輸出国に発生していない病害虫等の駆除の方法等についての衛生条件整備や、その担保等について(防疫官が確認する等)の整備が必要です。」とのことでした。
このお仕事を引き受けて下さる粗飼料業者の方はいませんか? 先日調査してきたミャンマーでは、場所によっては三期作で稲ワラが豊富にあります。必要なら政府の中枢の方を紹介できます。
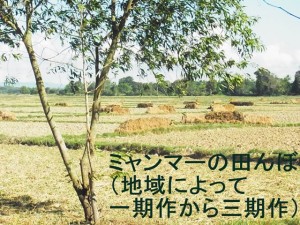

さて最後に稲ワラの輸入に関する条項をのせておきましょう。掲示板に堀さんもpdfファイルで詳細を乗せて下さっているので、そちらもご覧下さい。
************************************************
いねわら(稲わら)の輸入禁止の条項
○ 植物貿易法 昭和25年5月4日法律151号
(改正平成24・5・8)
(輸入の禁止)
第7条 何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入入してはな
らない。
ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産
大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
1 農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農
林
水産省令で定めるもの
2 検疫有害動植物
3 土又は土の付着する植物
○ 植物防疫法施行規則 昭和25年6月30日農林省令第73号
(最終改正:平成19年6月7日農林水産省令第59号)
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
第9条 法第7条第1項第1号 の地域及び植物を次のとおり定める。
(1) 別表2に掲げる地域及び植物
(2) 別表一に掲げる植物で、別表一に掲げる地域において野生しているもの
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
第9条 法第7条第1項第1号 の地域及び植物を次のとおり定める。
(1) 別表2に掲げる地域及び植物
別表2
地域
朝鮮半島及び台湾を除く諸外国
植物
いね、いねわら(かます、むしろその他これに準ずる加工品を含む。以下同じ。
)
(付表第29に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら
備考(対象とする検疫有害動植物)
イネクキセンチュウ、トリココニス・カウダタ、バランシア・オリゼーその他の
日本に産しない
各種の検疫有害動植物
付表29
中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであ
つて
農林水産大臣の定める基準に適合しているもの
前の記事 イナワラについて思っていること | 次の記事 新年のご挨拶 |
![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)