 |
第197話「子牛の下痢が悩ましい!⑲~クロストリジウムとの闘い~」 |
コラム一覧に戻る
2018年8月8日
細菌編の最後を飾るのはクロストリジウムです。
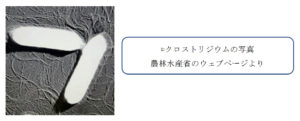
人間の世界ではクロストリジウム(以下クロスト)の1種であるボツリヌス菌がよく食中毒を引き起こすことで有名です。ボツリヌスって怖いイメージですよね。
細菌自体は偏性嫌気性細菌という種類で「酸素に触れると死んでしまう」という特徴があります。なんだ!じゃあ、牛さんの体に入るころには空気に触れてるから死んでるじゃん。安心だね♪、とはなりません。
なぜなら、ちょっとでも生命の危機を感じると「芽胞」という硬いカプセルのようなものを形成しそれに閉じこもってしまうからです。
芽胞を形成すると、酸素に触れようが、100℃の熱にさらされようが、数十年乾燥した環境におかれようが、死ぬことはありません。芽胞の間は休眠状態ですが、ひとたび生存に適した環境(それこそ酸素がない消化管の中は絶好の住処です)に身をおくとすぐさま増殖や生命活動を再開します。
このクロストは子牛から成牛まで感染、発症時期は幅広いのも特徴です。
とくに肥育末期ではビタミンA欠乏などで基礎免疫力が下がっている牛さん、慢性的なアシドーシスで腸内細菌が乱れている牛さんで重度の下痢や血便をもたらします。命に係わることも多く、非常に危険なおそろしい細菌です。
「芽胞」がよく見つかるのは土の中。
泥のついた草にはアイツがいるかもしれません。
雨が続いて地下水が濁っていれば、アイツがいる泥水が混じっているかもしれません。
感染を予防するためにも、土には十分な注意が必要ですね。
下痢や血便を見かけたら、「コクシジウムや!」となる前に、「クロストかもしれないな!」という発想も結構重要です。ペニシリンやアンピシリンで倒せる細菌ですので、サルファ剤との併用がおススメです。
前の記事 第196話「月末奮闘記」 | 次の記事 第198話「子牛の下痢が悩ましい!⑳~ロタ・コロナ~」 |